保護を実感できないイスラエルの民 出エジプト19:1-2
『◆シナイ山に着く
イスラエルの人々は、エジプトの国を出て三月目のその日に、シナイの荒れ野に到着した。彼らはレフィディムを出発して、シナイの荒れ野に着き、荒れ野に天幕を張った。イスラエルは、そこで、山に向かって宿営した。(出エジプト19:1-2新共同訳)』
荒野の移動で、多くの人が命を保ち続けていることが不思議で、まさに神業なのだと考えています。
これだけ多くの人たちが、水と食料を与えられて、創造主である神の保護で命をつなぐことができていたのです。
イスラエルの民にとっては、それは当たり前と受け止めていた部分と、そうではないと受け止めていた点がありました。
出エジプトさせたのは、創造主である神なので、生きられるようにするのは当たり前というアプローチもありました。
そして、こんなことなら、エジプトにいた方がよかったという、奴隷根性と表現するとキツいかも知れませんが、不遇な時代を懐かしむメンタリティーです。
元々、イスラエルの民=ユダヤ人は、交渉上手な人たちなのかも知れません。
それは、今の時代でも受け継がれている一面でしょうね。
モーセが間に入っているとはいえ、創造主である神を相手に交渉するのですから、その度胸はスゴいと感じます。
ユダヤ人の逞しさは、流浪の民と呼ばれるようになった歴史でもわかるように、世界のどこでも生きて行かなければならない将来への備えでもあったのかも知れません。
この時は、奴隷状態から引き出された(エクソダス)のですが、奴隷メンタリティからの引き出し(エクソダス)も必要だったのですね。
人間は、手厚い保護を受けていても、それを意識できない鈍感さもあります。
知らないことがよいケースも、知らなくてもよいこともありますから、せめて保護があることだけは感謝の気持ちを持ち続けていきたいですね。
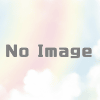
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません